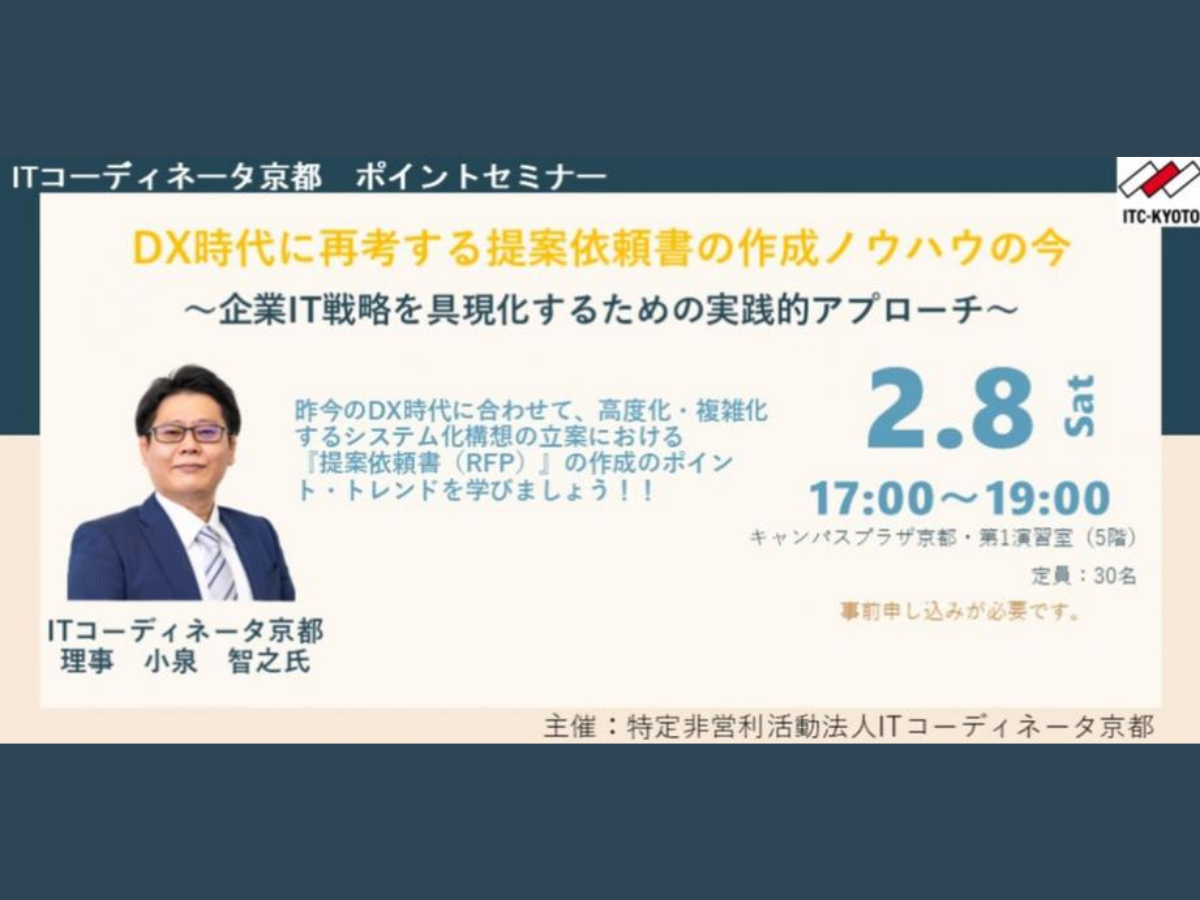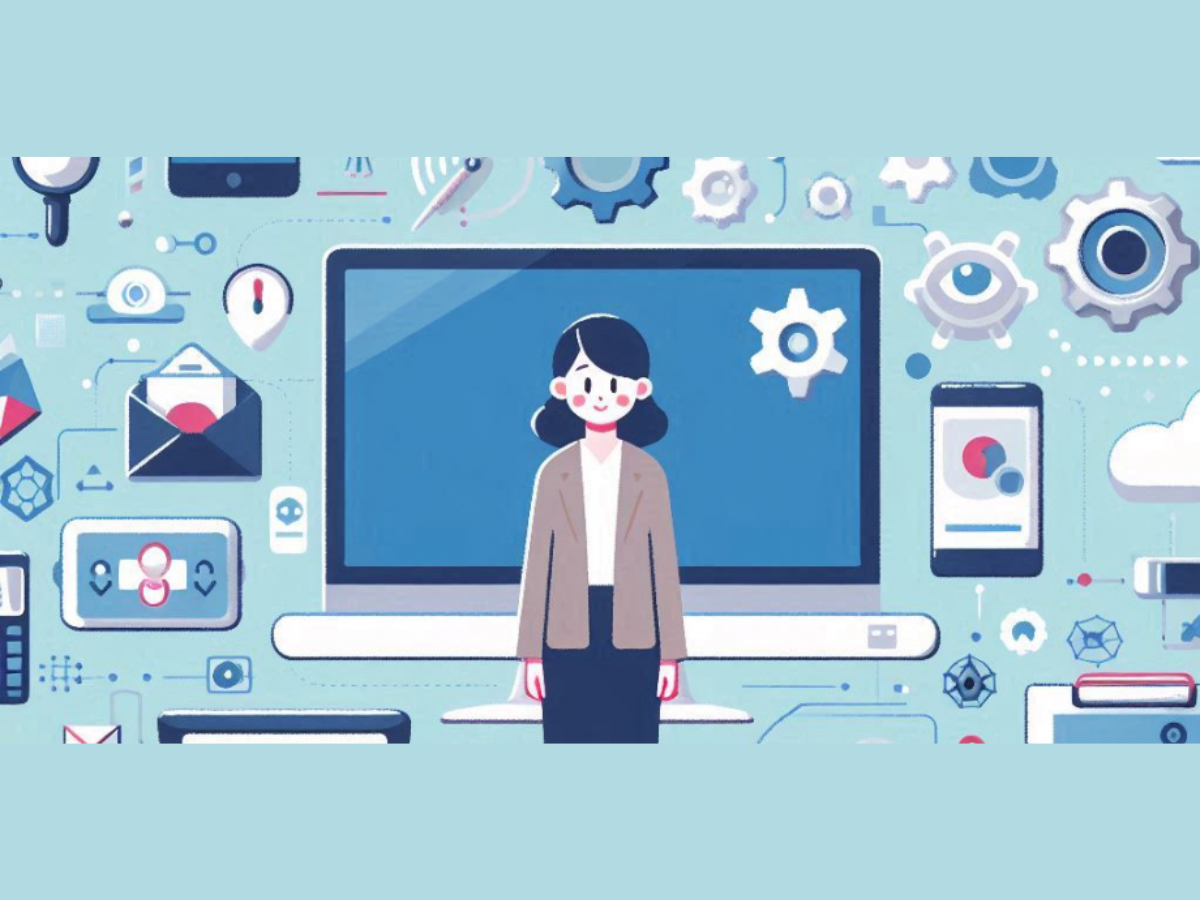はじめに
現在、人手不足や賃上げについて盛んに報道されています。こうした状況は中小企業の経営環境に大きな影響を与えていると考えられ、場合によっては、危機的な状況をもたらす可能性もあります。大企業と比べ相対的に財務体力が乏しい中小企業では、思い切った賃上げもままならず、人手不足に見舞われて、事業がシュリンクしていく可能性があるのです。では、どうすればいいのか。そうしたことについて、少し考えてみたいと思います。
エッセンシャルワーカーと人手不足
昭和時代の遺物(?)に、ホワイトカラーとブルーカラーという言葉があります。その場合、大卒はホワイトカラー、非大卒はブルーカラーというイメージです。しかし、この「ブルーカラー」が、コロナ禍のただ中で「エッセンシャルワーカー」と呼ばれるようになりました。つまり、社会にとってなくてはならない人々であることが認識されたのです。ある種のホワイトワーカーは少々いなくなってもとりあえず困らないが、エッセンシャルワーカーはいなくなった瞬間に社会が回らなくなる。そう認識されるようになったのです。中途半端なホワイトカラーはむしろ早期退職などの対象になるでしょう。しかし、エッセンシャルワーカーは顧客と直接かかわる現場仕事なので、いなければたちまち立ち行かなくなるのです。
しかも、このエッセンシャルワーカー層は現在人手不足に見舞われています。建設、運輸・配送、小売り、飲食、観光、介護、保育、看護、部品製造業などなど、多くが人手不足で悲鳴を上げている状態です。一番大きな影響は少子化でしょう。新たに労働市場に参入してくる若者の数が年々減っています。周知のように、これはさらに進んでいくでしょう。しかも、日本は技能実習や特定技能といった仕掛けを作らなければ移民を受け入れられない国です。ヨーロッパやアメリカのように大量の移民(つまり労働者)が流入してくることはちょっと考えられません。もう一つ言うと、大量にいた団塊世代も後期高齢者となり、高齢労働者市場も人口ボーナス期が過ぎてしまっているのです。
中小企業の危機
エッセンシャルワーク企業は、一部を除いてその多くが中小企業(せいぜい中堅企業)です。そのため、この人手不足は中小企業を直撃しています。中小企業経営は重大な危機に直面していると言っていいでしょう。働き手がいなければ、事業を縮小せざるを得ません。とすると、企業としてどんどんシュリンクしていって最後は立ち行かなくなるということが予測されます。しかも当面(2、3年ではなく、何十年にもわたって)この状態は続きます。手をこまねいて見ているわけにはいきません。中小企業の経営者は抜本的な対策を求められているのです。
対策1:少ない働き手でも事業を回るようにする
では、何をすればいいのか。ポイントは2つあると思います。一つは、少ない働き手でも事業が回るようにすること、いま一つは賃金を上げて働き手を獲得することです。まず、前者から。少ない働き手でも事業が回るようにするとは、要するに効率化の問題です。しかし、人が減っても業務が回るというのはきわめて高水準の効率化です。5人でやっていたのが、4人になり、3人になり、2人になっても業務が滞らないというイメージです。それをいかに実現していくかが問題になっているのです(もちろん、ブラック化は論外です)。効率化といえば、DXやAIを入れたり、製造業だとロボットを導入したりすることが思い浮かびます。しかし、それらは電子レンジのように買ったその日から簡単に使えるといったものではありません。どのように業務に組み込むのかを徹底的に考え抜かなければ機能しないでしょう。一般に中小企業は日々現場業務に携わっている従業員が大多数を占めます。DXやAIの導入といっても、余力がないのが実情です。とすれば、現場任せにするのではなく、会社を上げた取り組みが不可欠となります。会社として意志決定をし、ビジョンを伝え、計画し、体制を整え、動機付け、推進していくといったことが不可欠なります。とすれば、経営者の強い姿勢が何より必要となるでしょう。導入などの細かい手法の前に、まず経営者が強い思いとビジョンを持つが重要なのです。
対策2:高付加価値で利益率を上げる
2つ目は、働き手を獲得することです。そのためには賃金を上げることが不可欠です。エッセンシャルワーカー労働市場の需給バランスから言って、今後賃金は上昇せざるを得ません。人材が不足している以上、避けられないのです。とすれば、労働市場における賃金上昇についていき、さらにそれを上回るような待遇を提示することにより、人材が集まる企業になれるかどうかが、これからの中小企業の航路を決定づけると考えられます。では、そのためにはどうすればいいのか。端的に言ってしまえば、利益率を上げるしかないでしょう。利益こそがキャッシュを生み、キャッシュこそが高い賃金を払える原資となるからです。利益が十分でなければ原資が不足し、ない袖は振れなくなり、低賃金に甘んじることになって、働き手が離れていくことにもつながるでしょう。おそらくここに中小企業の最も大きな課題があるのではないかと思います。高い利益率を実現しようとすれば、高付加価値な事業を立ち上げ、高くても売れるような商品サービスを市場に投入する必要があります。もちろん、従来からやっている既存事業において適正な価格で売っていくということは重要です。しかし、それは不当に安い価格というマイナスを解消するにすぎません。プラスを獲得していくことが何より求められているのです。
多くの中小企業にとって(もちろん、例外はあります)、この高付加価値の事業を立ち上げることが最もハードルが高いのではないでしょうか。これはいわばイノベーションということに通じます。他にはないようなイノベーティブな商品サービスを市場に提供することによって、高くても売れ、高い利益を上げることができます。従来からやっている既存事業において漸進的に利益改善をしていくということは、多くの企業でやっておられるのではないかと思います。しかし、それでは高い賃金を払い続ける体力を長期にわたって構築してくことは難しいでしょう。他社がやっていないような事業、いままでにないような商品サービス、それを創出できなければ、どんどん労働人口が減っていく市場で5年後、10年後、20年後の未来は描けなくなります。では、そのためには何が必要か。一点だけ言えば、「挑戦する」ことだと思います。こう言うと、何とも陳腐なことに聞こえるでしょうが、実際やるとなると簡単なことではありません。挑戦するとは、要するに、どう転ぶかわからない領域に足を踏み入れていくことです。企業経営には確実性が必要でしょう。この手を打てば高い確率で売上が上がるといった確かな見通しがなければならないでしょう。こうした確実性をベースとした経営を続けていると、どう転ぶかわからないようなことに手は出せなくなります。要するに挑戦できなくなるのです。しかし、いままでにないような商品サービスを創出しようとすると、いままでないわけですから、確実な見通しは望むべくもありません。どうなるかわからないが踏み出していく以外ないのです。つまり、リスクをとれるかどうかが経営者として極めて重要になってきます。その意味で、ここでも経営者の強い姿勢が不可欠になるでしょう。
最後に:問われるのは経営者の姿勢
こう考えてくると、現在の危機を乗り越えていくためには、経営者の姿勢が極めて重要であることがわかります。これまでやってきた既存事業の延長線上から脱して、会社を創り変えていく覚悟が必要になるのです。DXやAIといったことが盛んに言われていますが、こうしたことが効率化面でも、高付加価値創出面でも、本当に有効に働くには経営者の強い思いと覚悟が不可欠なのです。それさえあれば、エッセンシャルワークは社会になくてはならない価値を生み出すのですから、必ずや世の中に不可欠の企業になっていけるのではないでしょうか。
◆執筆者プロフィール
清水 多津雄(しみず たつお)
CPC創発経営研究所 代表
ITコーディネータ
企業の情報システム部門でITマネジメントに従事したのち、イノベーションマネジメントに取り組み、創発的な経営方法を研究。2018年CPC創発経営研究所を設立。2020年「創発経営」で商標登録。現在、創発経営に基づく中小企業の経営サポートに従事している。