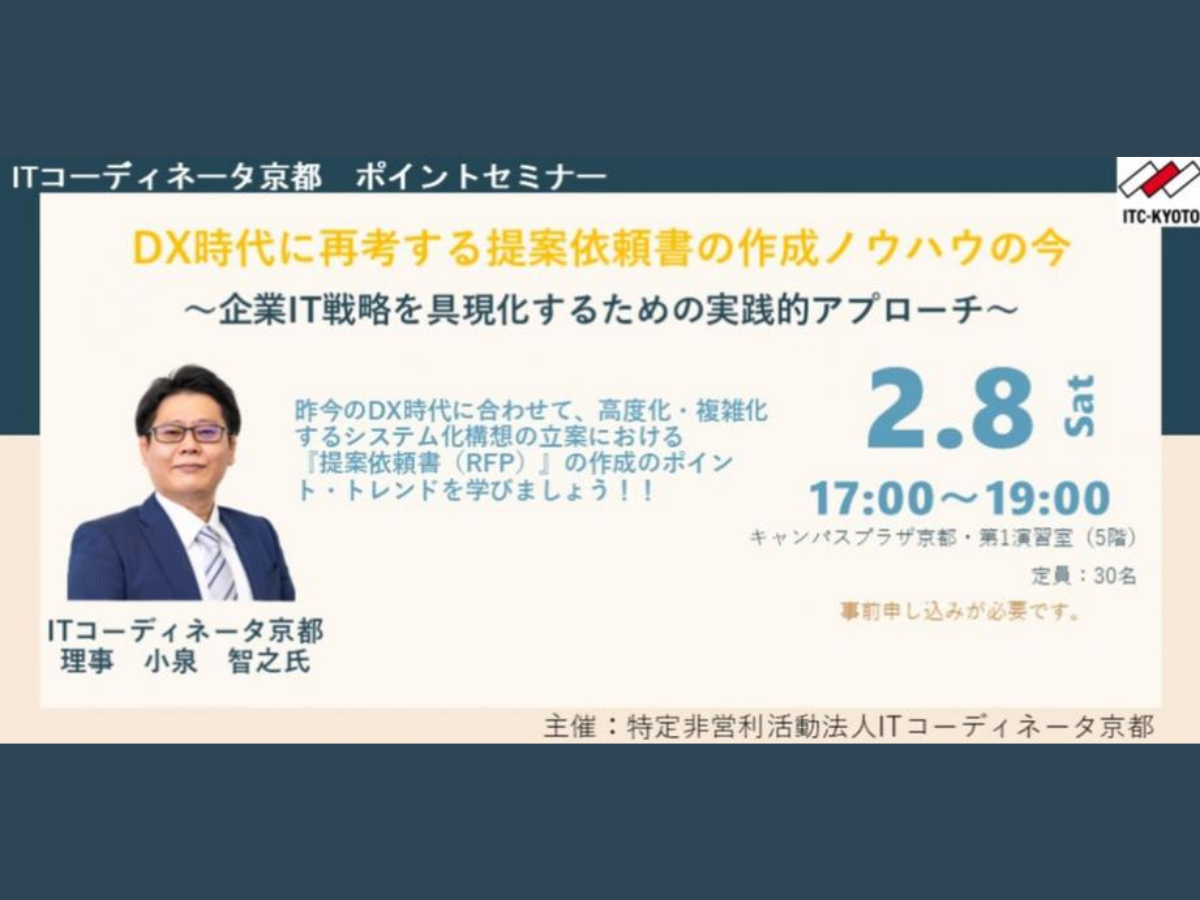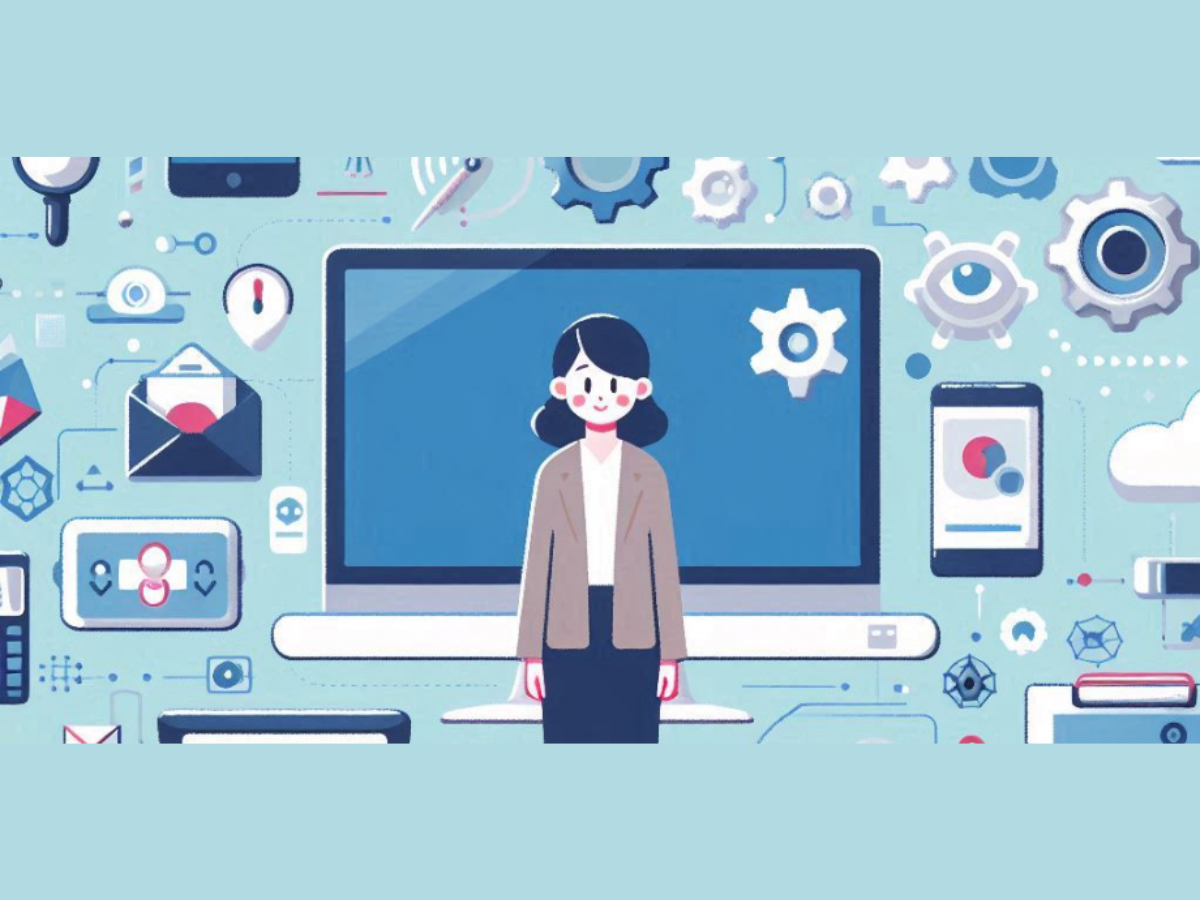2021年12月16日に旭化成さんは「旭化成における「デジタル×共創」によるビジネス変革」というタイトルで同社のデジタル戦略について説明会を開催されました。
ここで公開されたのが同社のデジタル変革のロードマップで、その後毎年12月に進捗状況を発表されています。
2016~2019:デジタル導入期
2020~2021:デジタル展開期
2022~2023:デジタル創造期
2023~2024:デジタルノーマル期
上記の様に、いわゆるデジタルエンタープライズになるまでのロードマップを会社として設定し、経営幹部が中心となってその推進を進めています。
第1期にあたる「デジタル導入期」のテーマは「現場に密着し実課題をデジタル技術で解決」で、実に400ものデジタルテーマが実施され、様々なデジタル技術を使って、現場の課題が解決されました。そして、この過程を通じて、多くの社員がデジタルを使って何ができるのかということについて体感できるようにしたわけです。
第2期の「デジタル展開期」では導入期で得られた知見を定着させるために、DXビジョンを作成し、社内の推進体制を整備し、全社員がデジタル人材となるべく社員教育を実施しています。デジタル人材のレベルとしては5段階設定されていて、一般社員はレベル3を、DX推進役となるデジタルプロ人材はレベル5を目指すものとしています。
2022年の発表では社長・会長がレベル3に到達したことが公表されていました。これは一般社員がDX推進の阻害要因にならないための強力なカンフル剤となっています。
そして第3期の「デジタル創造期」でいよいよデジタルを活用した新ビジネスの創造に着手します。ここでは、冒頭の常務さんの所属名にあった「共創」が大きな役割を果たすことになります。「社内社外と共創しながら、3つのフェーズを経て、新たな価値創造に挑戦する」としています。
・Co-Create (共に創る)
・Co-Execute(共に実行する)
・Co-Operate(共に運用する)
この第3期を経て2024年には「会社全体、全社員がデジタルを活用するのが当たり前になる」デジタルノーマル期に到達するという計画です。
欧米の企業は一般的にこの第3期にあるわけですが、日本では、いきなりこの第3期に取り組んで、デジタル組織やデジタル人材が浮いてしまい、とん挫した事例が多いです。これらの反省を踏まえた旭化成さんのアプローチは日本に合ったデジタル戦略であり、多くの企業がこのアプローチを見習っています。
ただ一部の企業を除き、残念ながら中小企業に限らず多くのDX事例は、デジタル導入期に相当するものばかりです。厳しい言い方をすればそれはDX事例ではありません。ITをデジタルに置き換えて効率化を実現したものでしかありません。
もちろん旭化成さんの様にロードマップを策定しているのであれば良いのですが、そうではなく、導入期のレベルでDXに取り組んだと勘違いしているものがほとんどです。
例えばECに切り替えたことをDX事例とされることも見かけますが、今や当たり前になっていることをようやくできるようになっただけという厳しい見方をされています。
中小企業の取り組みの多くは目の前の課題を解決して、それで安心してしまっています。DXはIT化とは全く異なり、デジタル化がどんどん進む世の中で会社はどのように生き残り、成長していくのか、そのシナリオを描くことであり、経営者が責任をもって作成しなければなりません。今の時代の経営戦略=DXと言い切っても間違いはありません。
デジタル化が進展している現状で、自社の事業が10年後も大丈夫なのか、まずは、その検討から初めて下さい。もし不安があるなら、次の事業の柱をどうするのかを検討してください。
小手先のデジタル化で満足している経営者や専門家はその考えを改めて頂きたいと願っております。
執筆者プロフィール
氏 名 宗平 順己(むねひら としみ)
所 属 武庫川女子大学経営学部教授
ITコーディネータ京都 副理事長
Kyotoビジネスデザインラボ 代表社員
資 格 ITコーディネータ、公認システム監査人
専門分野
・デジタルトランスフォーメーション
・サービスデザイン(デザイン思考)
・クラウド
・BSC(Balanced Scorecard)
・IT投資マネジメント
・ビジネスモデリング
・エンタープライズ・アーキテクチャ などなど